某年某日、春。娘の軽佻浮薄な行動を予期した父は階段下に陣取って動こうとしなかった。家出願望を強くしていた私、十九歳のときのことである。
変な男に誑(たぶら)かされ、娘が不幸にならぬよう思い定めた父は、一晩、いや七日七晩でも娘の前に立ちはだかるつもりであった。万に一つ、父の油断を飛び越えたとしても、妹の非難、兄嫁の説得と続き、兄の叱責の後には母の涙が待っている。
正面突破は無理だった。日本酒一升を半分空にしながら、私は窓を開けて下を見た。小さな疵が目に入った。気がついた時には、私は窓にぶら下がり爪先で疵を探り当て、口に銜えた車のキーを落とすまいと懸命であった。
あわや落下という状況のなか、私の素足は地を踏んだ。何故かわからないが、あらゆる価値観と反対を押しやって、私は一途にひとりの男に逢いに行こうとしていた。
片思いであった。それでも、車を一時間走らせ、遂には彼の腕に飛び込んで行くのだから、酒、いや恋とは思案の外である。私は当惑する彼に必死で訴えた。
「私、あなたがいないと生きていけないっ!」
結果として、この恋は実らなかった。いち早く異変に気づいた父によって私は連れ戻され、それっきり音沙汰のない恋となった。
なぜ今頃になって眠らせておいた恋を思い出してしまったのか。ワケがある。実は、あの《生きていけない》
というフレーズを私がン十年ぶりに口にした為である。
最近、川柳が辛くて仕方がない。言葉の迷路を抜けられないでいる。そんな状態でも、予定した大会や句会があれば行きたいのである。家族のために、カレーライスを作り、おでんを仕込み、洗濯物を残さず干していく。主婦の外出は、いろいろと気を遣う。
妻の不在を不満に感じないように、あれやこれやと手を尽すのだが、時間が近づくと、あきらかに夫は不機嫌な様子を見せる。曰く《主人の休みの日に外出するとは何事か》となる。最後には《俺と川柳とどっちが大切なのか》と詰め寄ってくる。まるで子供の言い分である。いつもなら、さらりとやり過ごして出かけるところだが、その朝の私はどうかしていた。ドアにかけていた手を離し、くるりと向きなおると、夫を見た。
「私、川柳がないと生きていけないの、呼吸困難になるの」
夫の呆れたような顔を、怒りとも憧れともつかない奇妙な表情がかすめ、最後はあきらめたように肩を落とした。そして、無言で右手をひらひらして見せた。《行けよ》ということらしい。私は、夫に一礼すると、こちらも黙って後ろ手にドアを閉めた。
以来、夫は私の外出を黙認してくれるようになった。不思議なことに、川柳がないと呼吸困難になると自覚した途端、なぜか身のうちに巣くっていた私の《辛さ》は薄らいできている。十九の春の熱っぽさが、私のなかにまだあると知ったためかも知れない。そんな気がする。
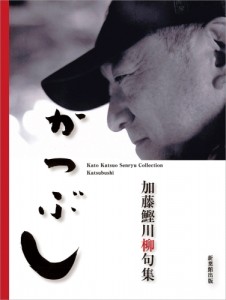 また、電子書籍も近日発行予定だそうです。
また、電子書籍も近日発行予定だそうです。