霜石コンフィデンシャル134 高 瀬 霜 石
「無芸(蕎麦)大食」 ―二枚目―
蕎麦に目がなくて、蕎麦屋の暖簾をくぐると、つい冷っこい蕎麦と熱っつい蕎麦の両方を注文してしまう癖があるのだと、前号で告白した。
1月の中頃、弘前市内の有名店「高砂」へ行き、いつものように「もり」の後「かけ」を頼んだ。
僕と同じくらいの年塩梅のオヤジが、反対側の席にいて、もりの後にかしわ蕎麦を食っていた。
彼が店を出た後に、僕も勘定に立ち、おかみさんについ訊いた。
「今出て行ったオヤジも、オラと一緒で冷っこいのと熱っつのふたつ食ったんでね?好きだねえ」
「蕎麦の写真も撮ってたけれど、メニューも撮っていいかって聞かれたので、ちょっと困ったけれど、旅の人みたいだから、どうぞって言ったの」と言う。
表に出たら、そのオヤジがまだいて、今度は店の回りもカシャカシャしていた。蕎麦好きのオヤジで、なおかつ旅人らしかったので、つい声をかけてしまった。
よく誤解されるのであえて書くが、僕は元来引っ込み思案の人見知り、知らない人に、あえてこちらから声をかけるなんて、普段はありえないことである。
「どちらからお越しですか?」
「東京です。それにしても、ここは珍しい蕎麦屋だなあ。いやどうしてって、蕎麦屋ってたいてい酒置いてるでしょう。それがここには、酒どころか、丼物もない。いや、ここまで徹すれば実に爽やか。見事だなあ」と褒めるから嬉しくなるではないか。
そこに、高砂のご主人がやってきたのには驚いた。
雪の路上で、まさかオヤジ2人が、蕎麦談義しているとは誰も思わないものなあ。ひょっとしてウチの蕎麦のナニかで揉めているのだろうかと、窓越しに心配になり、出て来たのだという。
東京の人と聞き、ご主人が若い頃修行した有名店や火事になった老舗とかで話が弾んだ。そうこうしているうちに―昼だもの、お客様がいるのだもの―痺れを切らしたおかみさんが、ご主人を迎えに出て来た。
そのオヤジは喜んだ。美人のおかみさんと是非記念写真を撮りたいと言うのだ。ついでに僕も入れて貰った。
「あの~、僕と30分でいいですから、お茶つきあってくれませんか?」だと。おかしいでしょ。続きは次号。
2014年5月号
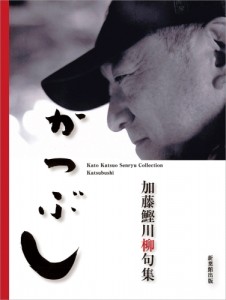 また、電子書籍も近日発行予定だそうです。
また、電子書籍も近日発行予定だそうです。